【MOVIEブログ】2016年ベスト映画本候補から3冊
岡田秀則さんが著した「映画という物体X」。発売されて直ちに購入した9月上旬、僕は東京国際映画祭の作品選定業務が「どピーク」を迎えていて、異常な精神状態にある時期だった。
最新ニュース
スクープ
-

3回目のキスシーンで「吸引レベル」。パク・ミニョンが“本当に驚いた”キスシーンの裏話
-

【MOVIEブログ】2016東京国際映画祭 総括のようなもの
-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】
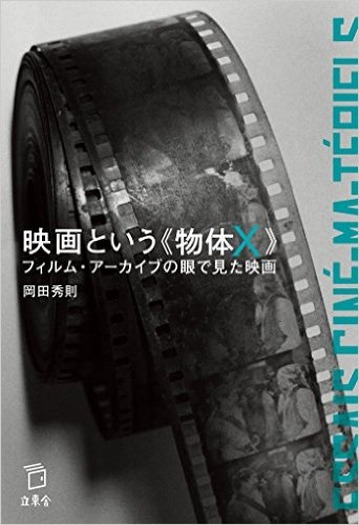
数ページ読んで、「この本はやばい」と感じ、映画祭が終わるまで封印しようと慌てて閉じた。読んでしまうと、まともに映画祭の仕事ができなくなってしまいそうな危険を感じたのだ。映画を「選ばない」というアーカイブの仕事に対し、「ひたすら選ぶ」映画祭従事者として、ねじれた憧れを感じてしまいそうだったから、というのは表向きの理由で、実際は岡田さんのあまりに魅力的な語り口に打ちのめされてしまい、仕事を続ける気が無くなってしまうかもしれないと思ったのが正直なところだ。
そしていよいよ映画祭が終わり、満を持してじっくりと読んでみた。予想にたがわず、気持ちよく打ちのめされた。映画という物質が辿る旅の、時空を超えた、まさにドキュメント。今年最も刺激と驚き(映画は牛だ!)を受けた映画本であり、言葉の選び方に最も興奮した本となった。さらに、無性に旅に出たくなる。映画本を読んでそんな気分になるなんて、なかなかないことだ。確かに映画祭前に読んでいたら雲隠れしていたかもしれない。危険な予感は当たっていた!
特筆すべきは、デジタル化によって過去の素材となってしまったフィルムに対するノスタルジアが微塵も感じられないことで、フィルムの保存がいかに未来に対して「攻める」行為であるかが伝わってくることだ。ノスタルジアがないのは、フィルムのことを忘れてしまったからではなく、フィルムに今日的意義が備わっているので懐かしむ必要がないからだ。本書は、ひたすら未来に向けて開かれている。
学術書ではないけれど、フィルム・アーカイブの仕事の内容とその神髄がよくわかるし、基本的に岡田さんのエッセイ風味も満載なので、ひとりの少年がいかに映画好きになり、シネフィルになり、そして映画を仕事にしていくようなったかを辿る、映画人半生記としてもとても面白い。映画という物質が辿る旅に、岡田さんの映画の旅が重なっていく展開がなんとも刺激的だ。
そして、映画とその周辺事項を叙述する際に用いられる魅力的な表現方法に僕はいちいち興奮してしまい、滅多にしない赤線引きを始めたら、止まらなくなってしまった。数ある映画本の中でも読んだことのないジャンルの本であり、日本映画本史に刻まれる貴重な一冊であると断言したい。
石井妙子さんによる「原節子の真実」は、何となく知っていると思っていた原節子に対する知識が、ことごとく間違っていたことを知らされる痛快な一冊だ。とても丁寧な評伝で、女優になるまでの子ども時代が丁寧に語られる。著者の想像力が発揮されている部分も多いと思われるものの、十分な説得力を持って原節子のひととなりが胸に迫ってくる。
デビュー直後のアーノルド・ファンク監督との出会いや、プロパガンダ映画としての『新しき土』について、そして同作を伴った欧州キャンペーンツアーのくだりが丁寧に描写される。当時の原節子の心情が生き生きと伝わり、思わず本人の手記かと思ってしまうほどだ。しかし、資料に裏付けられた描写であり、筆者の筆が滑っている印象は微塵も与えないところが本書の優れている点でもある。
本書を読めば、世間が夢見た小津監督とのロマンスなどは、全くありえなかったことがよくわかる。それどころか、原節子本人は小津作品を自分の代表作に挙げていないという指摘は驚きだ。小津作品どころか、いまだ自分には代表作と呼べる作品がないと考え、自身の企画の実現を追い求めた事実からは、ストイックな大女優の別の(真の)顔が見えてくるようである。
義兄である熊谷久虎との関係については、当然のことながら下世話な想像を排し、冷静に語られる。ふたりに男女の関係があったのかどうかについて本書はほとんど興味を示さないけれども、熊谷から原節子が思想的な影響を受けているという点については、かなり克明な言及がなされている。女優活動がスローダウンした時期の空白の日々に、原節子がどこで何をしていたかを探る筆者の情熱は執念にも似て、本書にただならぬ迫力を漂わせることになる。
では本書が原節子の恋愛沙汰に全く無関心であるといえば決してそうではなく、いくつかの「初恋」説の裏を取り、知られざる存在である男性の証言も取り上げられ、真に迫る。どうして原節子は生涯独身であったか、すでに無数の説があるのだろうけれど、本書を読めばすんなりと腑に落ちる気がする。本当に、こういうことだったのだろうと思わされる。
とにかく、慣れ親しんできた原節子の出演作の見方が、今後すっかり変わってしまいそうな気さえする。その多くが日本を代表する作品と目されているだけに、本書はひとりの役者の評伝を越えて、日本映画史を再批評する試みであるとも言える。これまた、今年の最重要映画本の1冊であると言い切ってしまおう。
今年最重要映画本は、まだまだある。春日太一さんによる「鬼才 五社英雄の生涯」は、その筆頭に来るべきもの。五社英雄という人物について、僕は(映画作品以外は)全く何の知識もないに等しかったので、まさにむさぼるように本書のページをめくることになった。
春日さんは大傑作の「あかんやつら」が今年文庫化されたり、来年早々には鬼平犯科帳を題材にした本が出る予定だったり、現在最も精力的に活動をされている映画作家(という呼び方をしたくなる)だ。その勢いに乗るように、「鬼才 五社英雄の生涯」の文章は流麗であり、力強い。
「力強い女性映画を得意とし、大変に怖いであろう人物」というパブリック・イメージを、時には裏付け、時には裏切っていくエピソードの集積に、徹頭徹尾興奮させられっぱなしである。春日さんの文体は、クールに事実を並べ、資料的価値を重んじて記述したような個所と、ドラマチックに人間性を描写するウェットな個所とが並存している点が素晴らしい。細部を大切にしながらも、全体としてダイナミックな読み物として成立しており、リーダビリティーがあまたの映画本の中で群を抜いている。
映画という虚実と、五社英雄という稀有な個性の虚実を交差させながら、じりじりと五社英雄の人物像に迫っていく様は、サスペンス小説にも似た興奮を与えてくれる。特に(本人のホラを交えた)刺青に関するエピソードは重要で、五社英雄の図抜けた創造性と繊細な内面性が長年にわたって混在した結果として、実に象徴的な形で語られる。本書を貫く主題がこのエピソードから浮かび上がってくるようだ。
とにかく、五社が手掛けた作品を全て見たくなる。映画本の優劣に対する分かりやすい判断基準のひとつが、登場する映画を見たくなるかどうかであるとしたら、もうこれ以上の本はないくらいである。本書を読みながらDVDを見ることが、今年の年末年始休み最大の至福をもらたしてくれるに違いない。誰もが知っていながら、誰も知らない五社英雄という人物に注目してくれたことを筆者に感謝したい。
特集
この記事の写真
/







