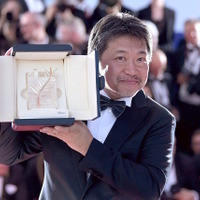【MOVIEブログ】2019カンヌ映画祭予習<「ある視点」編>
カンヌラインアップ予習の第2弾は、第2コンペ的位置付けの「ある視点」部門をチェックします。全18本です。
最新ニュース
スクープ
-

Netflix「マンスリー彼氏」でBLACKPINKジスが着た衣装は250着?ソ・イングクも演じた役の魅力を語る
-

【MOVIEブログ】2019カンヌ映画祭予習<コンペ編>
-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】

【「ある視点」部門】
『The Invisible Life of Euridice Gusmao』(カリム・アイヌズ監督/ブラジル)
『Evge』(ナリマン・アリエフ監督/ウクライナ)
『Beanpole』(カンテミル・バラコフ監督/カバルダ・バルカル共和国)
『The Swallows of Kabul』(ザブー・ブライトマン&エレア・ゴベ=メヴェレック監督/仏)
『A Brother’s Love』(モニア・ショクリ監督/カナダ)
『The Climb』(マイケル・アンジェロ・コヴィノ監督/アメリカ)
『Joan of Arc』(ブリュノ・デュモン監督/フランス)
『Chambre 212』(クリストフ・オノレ監督/フランス)
『A Sun That Never Sets』(オリヴェール・ラクセ監督/フランス)
『Port Authority』(ダニエル・レソヴィッツ監督/アメリカ)
『Papicha』(ムニア・メッドゥール監督/フランス)
『Nina Wu』(ミディ・ジー監督/ミャンマー)
『Liberte』(アルベール・セラ監督/スペイン)
『Bull』(アニー・シルヴァースタイン監督/アメリカ)
『Adam』(マリアム・トゥザニ監督/モロッコ)
『Summer of Changsha』(ズー・フォン監督/中国)
『The Bears' Famous Invasion of Sicily』(ロレンツォ・マットッティ監督/イタリア)
『Odnazhdy v Trubchevske』(ラリサ・サディロヴァ監督/ロシア)
全18本中、長編1作目が7本あります。若手発掘にも力を入れる部門です。作品によって情報量に偏りがありますが、1本ずつチェックしてみましょう。
『The Invisible Life of Euridice Gusmao』 (カリム・アイヌズ監督/ブラジル)(写真)
アイヌズ監督は2014年の『Praia do Futuro』がベルリン映画祭のコンペに入っています。あまり記憶にないので当時のメモを読み返してみると、僕は全く気に入らなかったらしい。ブラジル人とドイツ人の男性の恋愛を描いた内容に対して、異性愛だったらとても陳腐で見ていられない物語が同性愛だと許されるのだろうか、と大変憤った感想が書いてある。そうだったっけかな…。
新作は、1940年代のリオデジャネイロを舞台に、フェミニズム運動に身を投じるふたりの姉妹の姿が描かれるとのこと。前作の感想はいったん忘れることにして、まっさらな心で臨むことにしよう。え?2時間25分?むむ、どうしようか…。
『Evge』 (ナリマン・アリエフ監督/ウクライナ)
アリエフ監督は92年生まれの26歳、本作が長編1作目です。
亡くなった長男を故郷のクリミアで埋葬すべく、父親が次男とともに遺体をキエフから運ぶ…、と物語紹介にあります。
タイトルEvgeの意味が分からないのですが、ロシア語でグーグル翻訳をかけると「追い出す」という意味が表記されました。ロシアによるクリミア半島の併合が作品の背景にあるのかどうか。あるに違いないという気がしますが、これは是非観ておこうと思います。
『Beanpole』 (カンテミル・バラコフ監督/カバルダ・バルカル共和国)
IMDB(インターネット・ムービー・データベース)には、バラコフ監督の出身国はカバルダ・バルカル共和国、とあるのですが、大変恥ずかしながら、僕ははじめてこの国の名前を知りました。ウィキペディアによれば、「ロシア連邦の連邦構成主体のひとつ」だとのこと。ということは、ロシアなのかということなのだけど、となると上述のウクライナのクリミア地域もロシアであると呼ぶことになってしまいそうで、ここは国際政治的無知(音痴)を晒す前に先に進んだ方がよさそうです(ネットの「にわか知識」ほど怖いものはない…。これを機にちゃんと勉強しよう)。
バラコフ監督は長編1作目の『Tesnota(Closeness)』(17)が同じくカンヌの「ある視点」に選ばれ、国際映画批評家連盟賞(FIPRESCI賞)を受賞しています。僕は未見なのですが、同僚のコメントを確認してみると賛否が別れていたようで、対立する親子の関係を軸に、民族対立や民族浄化問題が描かれるドラマでした。説得力を認める意見がある一方で、焦点が絞りづらい作品であるとの見方もありました。
91年生まれのバラコフ監督の2作目となる本作は、2次大戦後のレニングラードを舞台に、がれきの山と化した街の中から再起を期すふたりの若い女性の姿を描いているとのこと。
ウクライナやロシアから20代の監督が台頭してくる現状にはとても興奮させられます。今年の「ある視点」の目玉のひとつになるかもしれません。
『The Swallows of Kabul』 (ザブー・ブライトマン&エレア・ゴベ=メヴェレック監督/仏)
実力派女優として知られるザブー・ブライトマンの監督作としては、何と言っても1作目の『記憶の森』(01)の印象が強く残ります。若年性アルツハイマーを病む女性を演じたイザベル・カレにとっても代表作であるでしょう。本作はブライトマンの5本目の長編監督作品であり、アニメーターのエレア・ゴベ=メヴェレックを共同監督として迎えたアニメーション作品です。
1998年、タリバンが占拠するアフガニスタンの首都カブールを舞台に、暴力や貧困がはびこる過酷な日常の中で愛し合う恋人たちの物語。将来を誓い合うものの、男の分別を欠いた行動のおかげでふたりの運命は狂っていく…。
原作はフランス在住のアルジェリア人作家、ヤスミナ・カドラによる「カブールの燕たち」で、これは日本でも翻訳が出ています。ザブー・ブライトマンに加え3人の名前が脚本クレジットに見られますが、恋愛劇とはいえ社会派ドラマを実写ではなくアニメで映画化を試みるあたりがフランスらしいですね。なかなか日本では海外の社会派アニメーションは公開されないので、これは何とかカンヌで観ておきたいところです。
『A Brother’s Love』 (モニア・ショクリ監督/カナダ)
モニア・ショクリはカナダの女優で、グザヴィエ・ドラン監督作『胸騒ぎの恋人』(10)でドラン演じる主人公青年の親友の女性を演じて注目を浴びました。本作はショクリの初監督作品で、脚本も自身が手掛けていますが、出演はせずに演出に専念しているようです。
舞台はモントリオール。美人で大卒だが職がないソフィアは兄のカリムの家に居候している。2人は仲がいいが、カリムがソフィアの婦人科医に深く恋をしてしまい、事態が変わってくる…。
タイトルそのままのプロットですが、コミカルなのかシリアスなのか、どのようなタッチなのかはちょっと分かりません。ただ、ショクリ監督がグザヴィエ・ドランと近いことや、そのドランのおかげでフランス語圏カナダの作品が充実してきている近年の流れを見るに、かなり期待してよいと思っています。
『The Climb』 (マイケル・アンジェロ・コヴィノ監督/アメリカ)
本作が長編第一作となるコヴィノ監督の名前を今回はじめて知りましたが、調べてみるとプロデューサーや脚本家としてゼロ年代後半から活動しているようです。中でも、プロデューサーとしてクレジットされている『キックス』(16)が少年映画の傑作と呼べる実に素晴らしい作品だったので、『キックス』がフィルモグラフィーにあるだけで一気に信頼できる気がしてきました。
本作は、「ふたりの男性の長年にわたる友情の物語」としか内容が分かりません。ただ、同タイトルの短編映画をベースにした長編であるようで、ロードバイク(自転車)を介在した男のドラマと短編の解説にあることから、少し想像を働かせることは出来るかもしれません。ほのかにコメディータッチのドラマなのかな…。
『Joan of Arc』 (ブリュノ・デュモン監督/フランス)
カンヌ常連のブリュノ・デュモン監督、今年は「ある視点」部門に参加です。近年は芸風が変わったというか、見たものを煙に巻くような常識外れの作品が続いて驚かせてくれていますが、今回は果たしてどうでしょう。
ジャンヌ・ダルクの少女時代を描いた『Jeanette』(17)は、デスメタルに乗せて聖女たちがヘッドバンキングしながら歌って語る天下御免の超ド級珍品でした。批評家筋には評価が高く、僕もそれなりに楽しみましたが(特に後半はいい)、あまりに難度が高く、戸惑ったのも正直なところです。とはいえ、デュモン作品は常にスキャンダラスな議論を巻き起こしてきたのであって、芸風が変わったという言い方は正しくないかもしれません。
新作の『Joan of Arc』はその正式な続編で、戦争での活躍から裁判に至るジャンヌ・ダルクの後半生が描かれるようです。主演の少女も『Jeanette』と同じ。そして今回もミュージカルであるようなのですが、ヘビメタではなく、主に80年代に活躍したフランスのポップシンガーのクリストフが音楽を手掛けるとのことで、かなり雰囲気は変わるかもしれません。とはいえ、もう観るまで全く分からない。かなり楽しみな1本です。
『Chambre 212』 (クリストフ・オノレ監督/フランス)
昨年は『Sorry Angel』(18)でコンペに出品していたクリストフ・オノレ監督、新作は「ある視点」部門でのカンヌ参加です。フランスの批評筋から強い支持を得るオノレ監督とはいえ、2年連続でカンヌコンペというのはなかなかハードルが高いのだなと思わされます。
前作は80年代を舞台に年の離れた同性愛やエイズの悲劇を含む(少し監督の自伝的かと思わせる)物語でしたが、今回はガラリと変わって長年の結婚生活に疲れた女性を取り上げています。
マリアは20年に及んだ結婚生活に終止符を打とうとし、家を出て向かいのホテルにチェックインする。ホテルの212号室からは自宅や夫や結婚そのものが見渡せる。マリアは自分の選択に疑問を抱き始める…。
出演はキャロル・ブーケ、キアラ・マストロヤンニ、ヴァンサン・ラコスト、バンジャマン・ビオレー(フランスの「ムンムン系」でキアラと結婚していた時期もありました)など豪華。もしかしたらコメディータッチなのかな?監督の前作にさほど反応しなかった僕としては、むしろ楽しみにしたい作品です。
『A Sun That Never Sets』 (オリヴェール・ラクセ監督/フランス)
ラクセ(LAXEの読み方に自信なし)監督はフランス人ですがスペインのガリシア地方にルーツを持ち、スペイン圏で映画を作っています。
前作『Mimosas』(16)はカンヌの「批評家週間」の作品賞を受賞しています。もっとも、僕の印象はさほど強くなく、山越えのロードムービーとして前半は観応えがあったものの後半に物語が散漫になってしまい、放り出されたままラストを迎えてポカンとしたことを思い出します。それでも作品賞を受賞したということは、それなりの力があるはずで、新作でそれを確認したいところです。
放火の罪で服役した男が出所し、母が暮らす故郷のガリシアに身を寄せる。穏やかな日々が過ぎて行く。しかし新たに山火事が発生し、地域を破壊してしまう…。
前作でも自然の力に立ち向かう人間の姿が映画の中心になっていましたが、本作もその延長線上にあるようです。作風に一貫性がある若い監督を発見して追いかける喜びは何物にも代え難いだけに、ラクセ監督がそのような存在になるかどうか、しかと見届けます。
『Port Authority』 (ダニエル・レソヴィッツ監督/アメリカ)
本作が長編監督第1作となるレソヴィッツ監督は、2017年に「監督週間」で上映されて高く評価された『Mobile Homes』で(共同)脚本を手掛けています。『Mobile Homes』はネグレクト気味の少年に対して若い母が愛を自覚して立ち直ろうとするドラマで、後味のよい佳作でした。あの脚本家が監督デビューとなると、俄然気になります。
ニューヨークに出てきたばかりの青年が、ヴォーグ・ダンスを踊る女性に恋をする。女性はヴォーギングを得意とするN.Y.のクイア・コミュニティーに属するトランス・ジェンダーであり、ストレートの青年は自分を見つめ直すことになる…。
LGBTテーマはもちろん、クールなヴォーグで痺れさせてくれることを期待したい!
『Papicha』 (ムニア・メッドゥール監督/フランス)
メッドゥール監督はアルジェリア系のフランス人。ドキュメンタリー作品を2本監督しており、長編劇映画としては本作が1本目です。
政治にイスラム色が濃くなり、女性の自由の制限が進行していた97年のアルジェにおいて、スタイリスト志望の若い女子学生が状況に抵抗すべくファッション・ショーを企画する、という物語。
明確なメッセージと意思を持つ作品であることは間違いないでしょう。タイトルの「パピシャ」というのはアルジェリアの若い女性を指す言葉だそうで、深刻さと華やかさがどのようなバランスで描かれているだろうかという点に興味を惹かれます。
『Nina Wu』 (ミディ・ジー監督/ミャンマー)
ミャンマー出身で活動のベースを台湾に置くミディ・ジー監督はすでに国際的に知られた存在です。ロッテルダム映画祭の常連であるなど各国の映画祭に出品も多く、『マンダレーへの道』(16)はヴェネチア映画祭でプレミア上映され、その後東京フィルメックスでも紹介されています。長編監督5作目となる本作で初のカンヌ参加。僕も彼の過去作全てが好きで、東アジア勢が少ない今回のカンヌでとても応援しています。
前作『14 Apples』(18)はドキュメンタリーとフィクションが見事に融合した作品で、不眠症に悩む男が占い師のすすめに従い、14個のリンゴを買って14日間僧侶になるという物語。長廻しのショットが効果的で映像のリズムがこの上なく心地よい傑作でした。
新作『Nina Wu』はフィクションですが、現実世界の出来事、特にワインシュタインの件や#Me Tooに触発された内容のよう。都会に出てきた女優志望のニナが長期の待機を経て、ついに映画の主役を掴みそうになるものの、過酷な選択を迫られてしまうという物語。
ミディ・ジーの作品に失望したことがないので、かなりいままでとは趣が異なりそうな本作も期待大で臨むつもりです。
『Liberte』 (アルベール・セラ監督/スペイン)
スペインの鬼才、と呼んでいいでしょうね、アルベール・セラ。怪作『ルイ14世の死』(16)で来日した際のアテネフランセで行った諏訪敦彦監督とのトークは凄かった。ひたすら一人でしゃべり続けた姿が脳裏から離れません(通訳のFさんが一番大変だった)。鬼才というか、天才肌なのでしょう。絶対に見る監督のひとりであることは間違いありません(と書きつつ、太陽王ルイ14世を再び取り上げた前作『Roi Soleil』を見逃している…)。
聖書のエピソードや歴史上の人物を描くことが多いセラ監督ですが、新作ではフランス革命を目前としたルイ16世の時代に、自由主義思想を持つが故に宮廷を追放された貴族たちを取り上げています。ドイツに活路を見出そうとする貴族たちの行動が主となるようです。
一筋縄で行くドラマであるはずがなく、実験映画色も強い内容になるのではないかと予想されます。心して臨むべし。
『Bull』 (アニー・シルヴァースタイン監督/アメリカ)
シルヴァースタイン監督の名は今回初めて知りましたが、本人のHPがあるので見てみると、テキサス出身のアメリカ人で、短編やドキュメンタリー作品を多く手掛けたのち、今作が長編監督第1作であるとのこと。2014年の短編作品がカンヌの学生部門で受賞しており、着実なステップアップを果たしてカンヌの公式部門入り、という存在です。
ヒューストン郊外のさびれた地で、身勝手な10代の少女が気難しい隣人の老人と衝突する。その老人はかつて闘牛士であり、過去の栄光とともに生きている。ふたりの衝突は互いを変えて行く…。
IMDB上の紹介文ですが、なんだかとても惹かれますね。「ある視点」に選ばれる新人監督の作品がほのぼの系であることはないとは思いますが、リアルなウェルメイド系を予想します。
『Adam』 (マリアム・トゥザニ監督/モロッコ)
トゥザニ監督はこれまでにモロッコの売春や児童労働に関するドキュメンタリーを手掛けたり、女優としても活動したりしていますが、本作が長編監督デビュー作です。今年の「ある視点」の新人監督の豊かさには驚かされます。
もっとも、アルジェリアやモロッコの映画界はフランス映画界と距離が近く、映画支援プログラムも充実しているようです。昨年マラケシュ映画祭を訪れた際にも、若手映画人たちの活気が肌で感じられました。上述のアルジェリアのムニア・メッドゥール監督とトゥザニ監督はともに北アフリカ系の女性監督で1作目という共通点があり、今年のカンヌを盛り上げる波になるかもしれません。
カサブランカでモロッコ菓子店を営む未亡人のシングルマザーが、突然若い妊婦の訪問を受け、ふたりの出会いは意外な運命へと繋がっていく…。
ふたりの女性の物語でありながらタイトルが「アダム」であることも気になります。ドキュメンタリーの実績から見てヘヴィーなリアリズム系を予想しますが、ガチで付き合います。
『Summer of Changsha』 (ズー・フォン監督/中国)
ズー・フォン監督の1作目長編。もともと俳優出身で、テレビシリーズや、中国共産党誕生の経緯を描いて話題になった『建党偉業』(11)で注目されているのですが、残念ながらいずれも僕は未見。今回は自らを主演にした監督作です。
本作については情報がなく(中国語が出来る人は中国のサイトに何か見つかるかもしれません)、分かることはと言えば、タイトルのChangshaとは中国の湖南省の長沙市であるということくらいで、「長沙市の夏」ということは青春映画かな…、でも主演の監督は74年生まれだから青春でもないか…、などと想像するしかありません。
もうひとつ分かるのは共演の女優がホアン・ルーであることで、彼女は昨年のフィルメックスで上映された『幸福城市』への出演が記憶に新しいです。ロカルノでグランプリを受賞したグオ・シャオルー監督『中国娘』(11)の主演や、ロウ・イエ監督の『ブラインド・マッサージ』(14)への出演など、欧州系映画祭では知られた存在と呼んでいいと思います。これは俄然期待が高まりますね。
『The Bears' Famous Invasion of Sicily』 (ロレンツォ・マットッティ監督/イタリア)
イタリアのアーティスト、ロレンツォ・マットッティによるアニメーション作品。原作はディーノ・ブッツァーティによる絵本の「シチリアを征服した熊の物語」(日本でも出ています)で、寒さと飢えに耐えかねた熊たちが山を下り、人間の住む町にやってきて様々な体験をする、というもの。
「独特のビジュアルと色彩は見る者を驚かせるだろう」とカンヌの公式HPに記述がありますが、素晴らしい映像が期待できそうです。本作と、上述の『The Swallows of Kabul(カブールの燕たち)』は、ともに6月のアヌシー国際アニメ映画祭のコンペ入りが決まっているとのこと。名優トニ・セルヴィッロはじめ、声優陣も豪華です。
『Odnazhdy v Trubchevske』 (ラリサ・サディロヴァ監督/ロシア)
カンヌのHPから選定コメントを粗約で抜粋します:「サディロヴァ監督はいままで5本の長編を手掛けている。ここ数年は新作が無かったが、今回現代ロシアの田舎を舞台にしたラブストーリーで戻ってきてくれた。役者が素晴らしく、演出は洗練され、監督の注ぐ目線が温かい。女性の期待や辛抱や勇気といったものが、あるいは自由や欲望やフラストレーションといった思いが、重々しくない形で検証されていく。カンヌは初めての参加となるサディロヴァ監督を歓迎する」。
僕はサディロヴァ監督の2007年の長編『Nothing Personal』を2008年のロッテルダム映画祭で観ているのですが、当時のメモを見てみるとほとんど記述がなく、あまり気に入らなかったようです。ああもったいない。いまとなっては記憶がないので、本当にメモをさぼってはいかんですね。11年後に役に立つこともあるのだから…。反省を込めてしかと見届けるつもりです。
以上、「ある視点」部門でした。これまた監督のキャリアについても、あるいは出品国やジャンルを見ても、多様性に富んだラインアップと呼べそうです。特に1本目の監督は今後の飛躍が期待できるので見逃せません。
「ある視点」部門の審査員は、委員長がナディーヌ・ラバキ(レバノン/監督)、以下、マリーナ・フォイス(フランス/女優)、ヌアハン・シェケルチ=ポルスト(ドイツ/プロデューサー)、イサンドロ・アロンゾ(アルゼンチン/監督)、ルーカス・ドン(ベルギー/監督)の5名。個人的にはイサンドロ・アロンゾを敬愛しているので、どのような審査になるか、この部門も楽しみです。
次回は、「スペシャル・スクリーニング(特別上映)」部門などを予習します!
《矢田部吉彦》
特集
この記事の写真
/