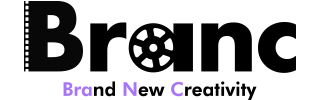第35回東京国際映画祭が都内、日比谷・銀座・有楽町エリアを中心に開催。会期中には様々なイベントが開催されており、10月30日(日)には丸の内マルキューブにて、「『ある男』×『百花』日本映画、その海外での可能性」と題し、日本映画の海外での可能性をテーマにトークイベントが開催された。
今回のトークイベントには、『ある男』がヴェネチア国際映画祭のオリゾンティ・コンペティション部門にてプレミア上映された石川慶監督、そして『百花』でサン・セバスティアン国際映画祭監督賞を受賞した川村元気監督が登壇。普段から親交があるという気鋭の監督ふたりが、海外映画祭やそれぞれの製作過程でみた景色、そして日本映画の海外での可能性について語り合った。
ふたりが海外の映画祭でみた景色とは?
芥川賞作家・平野啓一郎のベストセラー小説を実写化した『ある男』は安藤サクラ演じる⾥枝と、案件を依頼された妻夫木聡演じる弁護士が⾥枝の亡くなった夫の素顔に迫るヒューマンミステリー。本作は、今年のヴェネチア国際映画祭と釜山国際映画祭で上映された。

石川監督は、「妻夫木さんと初めてタッグを組んだのは長編を初めて撮った『愚行録』で、これもヴェネチアにいっていたんですが、その時は、妻夫木さんは出席できなかったんです。今回ヴェネチア国際映画祭には安藤さんは参加できず、妻夫木さん、窪田さんと参加したのですが、イタリアの観客の本作のキャストの知名度が高く、前回訪れたときと比べてアジア映画に対しての注目度を感じました。」と、ヴェネチア国際映画祭の様子を振り返った。
川村元気監督自身の体験を基にした小説を映像化した『百花』は主演に菅田将暉と原田美枝子を迎え、記憶を失っていく母、母との思い出を蘇らせていく息子のそれぞれの「記憶」の旅路を描いた物語。
本作で監督としてははじめてサン・セバスティアン国際映画祭に参加した川村監督は、「着いたときの塩対応から周りが優しくなっていく流れが面白かった」そうで、「コンペティションでホン・サンス監督が華やかな雰囲気で参加されていたり、プログラマーも呼んでくれたにもかかわらず、今回は最初だから期待しないで、という空気で、結構塩対応を受けていた。ただ、公式上映後に雰囲気が変わっていき、毎日クリティックス(映画評論)がよくなっていくごとに急にプログラマーも優しくなりはじめて、結果として、監督賞をとることができた」と話した。
映画をつくるとき、海外を意識している?
そして話は今回のテーマである、「日本映画は日本人にしか愛されないのか?」という話題に。
映画作品を企画・開発するときに海外を意識しているか?という司会者からの質問に対して、川村監督は「アニメーションは海外で受け入れられる地盤があるし、だからこそ作家性が強いものが作られやすいんですけど、実写になるともっと大変で、ドメスティックなヒットを狙うことと、海外で観てもらうことの両方を獲るのは難しい。一応ここにいる二人は頑張ってそこをやろうという話をしている。一番大事なのは企画、なにをやるかですよね。それを石川さんに何を基準に決めているか聞いてみたいです。」と石川監督に尋ねた。

石川監督は、「コマーシャルフィルムっていうのと、アートハウスフィルムのふたつがあるじゃないですか。アートハウス系っていうのはなんとなく外に出ていくイメージが自分の中ではわかる気がしているんですけど、コマーシャルなものは外にどう出していくかがいつも自分の中で大きい課題としてあって。ただ、企画段階では、実は外への意識をあまり持っていないし、あまり言わないようにしている。ポーランドで現地のクルーと制作していたときには、英語に訳していて面白くないものは絶対ダメだし、仕上げをしているときに何だこの映画?と思われるのは嫌なので、その辺りからこれはやりたくない、とか(感じます)。主題歌とかをあまり入れたくないのもそういった理由が大きいんですが。企画の立ち上がりでいうと、日本映画的な気がしている。」と答えた。
また、普段日本映画では日本の配給会社を決めてから海外にセールスするところを、今回『百花』では、海外の配給会社「ワイルド・バンチ」に早い段階で入ってもらっていたのだという。

川村監督は、「(パーソナルな物語なので、海外受けを意識して作った作品ではなかったが、)まずは腕試しだと思って脚本を英訳し、ワイルド・バンチに送り、読んでもらったら、『面白いから配給したい』と言ってくれて、これは、言語を超えて伝わる物語なのかなというところからはじまった。4年前に短編映画『Duality』でご一緒し、カンヌ映画祭にも一緒に行った佐藤雅彦さんが「つくりかたをつくることによってユニークなものが生まれる」と常々おっしゃっていて、だとしたら映画のつくられ方も、順番を逆にしてみたらどうだろう、という感じではじめたんです。」と、その理由を話した。
日本映画の魅力を海外の人たちにアプローチするには?
話は日本と海外での映画制作の違いに広がり、日本映画の特徴を分析。いまだに海外ではジャンル映画のように捉えられている、と話すふたりがこれからの日本映画を海外にアプローチするために必要だと感じることは何なのか。
アニメーションも経験している川村監督は、「アニメーションは(海外に)受け入れられている。今一番ストーリーテリングやキャラクターで尖ったことをやっているのは、実は週刊少年ジャンプの漫画家たちな気がするんですよ。「チェンソーマン」とかみているとすごいなと思います。海外とコミュニケーションをしている最前線がアニメにある感じはします。だから、ライブアクションのチームこそ尖ったことをやらないと表現がみな同じになっていってしまうかなと思います。」と実写映画への思いを吐露した。
また、これまで大手と組むことが多かった石川監督は、「難しいのは、国内興行第一主義というのがよく言われていて、でも、第二、第三はないよねと思いながら…。映画祭に出すときも、外の人に見てほしいのではなくて、国内興行にプラスするために外に出す、という外に向いているようで実は内向きの出し方になってしまっているから、それではなかなか映画祭からも注目されないですよね。是枝監督の作品のように、海外で見られる日本映画が増えていけば、外の出方の意味合いが変わっていくと思います。それが、韓国はうまく機能しているのでは」と語った。

日本の興行と海外の評価のギャップを埋めるには?
日本のアニメーション作品は世界で認知・人気が広がる一方で、実写作品はいまだ国内にとどまっている印象がある。その理由をふたりはどのように考えているのか?
石川監督は、「面白いものを作るのが大前提」と話し、続けて「例えばヴェネチアに行ったときに思ったのが、ヴェネチアは会場まで船で行くんですが、映画業界人や映画ファン、色々な人がいる船上で昨日のコンペのこの作品がよかった、よくなかった、など熱い議論がでたり、翌日には一般紙に批評が出るのがいいなと思って。東京国際映画祭ではコンペティションの話題がそんなにあがっておらず、映画の内容の話をもっと、社会全体がしていけるといいなと思います。」と映画祭への思いも語った。
また、川村監督は「テーマセッティングが重要」だという。「著名なアニメーション監督たちもテーマのセットアップに時間をかけていて、今の時代になにをつくり、映画が公開される2、3年後にどういう風に時代の空気とマッチするか、を考えている。映画祭に来る映画は最初からそういうところを意識して作っている。『百花』でも、そこはすごく考えました。」と、話した。
最後に、観客からの質問に答えた後、これからの世代へのエールとして、ふたりは、
石川監督「業界がささやかに連帯していくといいと思います。新しく入ってくる人たちもぜひ怖がらずに、ゆるい連帯の中にうまく入って大きい流れがでてくると。映画祭はそのためにあるという部分もあると思います」
川村監督「精神的な複眼をもってやっていくことがいいなと思う。ちっちゃいコミュニティにならないで、世代や関心が異なっても色んな人と話すことで、映画の多様性につながると思います。」とエールを届け、会場からは大きな拍手が起こった。
10日間にわたる東京国際映画祭は本日11月2日で閉幕する。