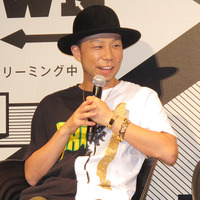【インタビュー・前編】バズ・ラーマンが語る、「ゲットダウン」に込めたヒップホップへのリスペクト
シネマカフェでは、「ゲット・ダウン」の撮影が行われたクイーンズのスタジオにて、製作総指揮を務めたバズ・ラーマンをはじめとするスタッフ、キャストにスペシャルインタビューを実施。
最新ニュース
インタビュー
-

チソン主演『二度目の裁判』が異例の快進撃!最高視聴率14.7%記録で“週末ドラマの王者”に
-
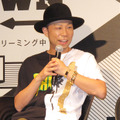
USA、ヒップホップ界隈の厳しい上下関係に「EXILEも体育会系」
-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】

“ゲット・ダウン”とは、楽曲の中で歌やメロディが鳴らされるメインのパートではない、ドラムとベースといったビートの部分のみ鳴らされ、リズムが強調されるわずかなパートのことを意味し、のちに“ブレイクダンス”、“ブレイクビーツ”などといった言葉で広まることになる“ブレイク”と同義でもある。DJは、あるレコードの中で“ゲット・ダウン”を見つけると、同じもう一枚のレコードを用意し、2つのターンテーブルとミキサーがあれば、ブレイクの部分を永遠にまで引き延ばすことができる。こうしてヒップホップのビートは“発明”され、MCはそこにライムを乗せ、ダンサーたちは新たなダンスを披露するようになり、ヒップホップというアートフォームが生まれたのだ。
フラッシュ:ブロンクスでは、この時期は俺たちにとっての実験的な期間だったんだ。いろいろなことを試すためのね。さっきバズが言ったように、当時はディスコが盛り上がっていた頃だ。最初、俺たちはポップやロック、ジャズ、ブルース、ファンク、ディスコ、R&B、オルタナティブ、そしてカリビアンのドラムなど、いろいろな音楽における“ブレイク”を、それまでこういうものを聞いたことがないかたちで観客に対して試すことができたんだ。
バズ:劇中で、若いときのフラッシュがこの主人公たちに向かって「これは魔法の力だ。でもただ渡すわけにはいかない」と言う。そうして神話を語るんだ。まるでカンフーのようなものさ。フラッシュがやっていたことは、ほかの人たちが音楽を作り出すのとは全く違うものだ。誰も考えつかなかったし、コラージュなどという言葉もなかった。彼は同じレコードを2枚使ってビートを繋げなければならなかったんだ。彼は片方のレコードを逆回転させて戻し、手で押さえておいてもう片方に繋げ、この感動的なフレーズを継続させていた。まるで循環呼吸のようなものさ。
ネルソン:フラッシュがバズに自分の秘密について話していたときのビデオを僕は持っているんだ。いまもどこかにあるよ。そのときの会話が作品の中にそのまま入っている。だからそのセリフは作り上げられたものではない。過去と現在を生きている彼の言葉さ。
ほぼ同年齢のフラッシュとネルソン。当時のことを語りだすと、自然と音楽談義に花が咲いていく。本作の劇中で使用される様々な楽曲の数々――それは77年当時を象徴する楽曲はもちろん、新旧交えた様々な楽曲が使用され耳を楽しませてくれるが、これらの選曲はネルソンが行っている。止まらない音楽談義の中で、日本人である取材陣を意識してか、「YMO」の名前まで飛び出した。
ネルソン:その夏のことが忘れられないよ。僕はニューヨークのブルックリンにいたんだけど、突然道の向こう側から大きなサウンドシステムの音がしたんだ。僕はちょうど寝ようとしていたところだったんだけど、向かいに住む男が「チッチチチッチチ…」と音を出し始めて、それが一晩中続いた。そして僕たちは「ヨーロッパ特急」(※ドイツのテクノグループ「クラフトワーク」による77年リリースのアルバム。のちにブロンクスのDJであるアフリカ・バンバータの「プラネット・ロック」にてサンプリングされた)を聞くようになった。僕はイースト・ニューヨークのフッド(黒人街)に住んでいたのに、そこにいる奴らはドイツのコンピューター化された音楽をかけていたんだ。
バズ:日本のバンドもあったよね。
ネルソン:「イエロー・マジック・オーケストラ」だよ!
フラッシュ:彼らのレコード手に入れたのを覚えてるよ。ダラス・ダンス・レコードのニックから電話をもらった。日本のレコードを手に入れたよ、と。「すぐ行く!」と言って、俺は電車に乗って行った。それで黄色いシースルーのレコード(※「YMO」のファーストアルバム「Solid State Survivor」のこと)を手に入れたんだ!
ネルソン:ああ、あの黄色いやつだ!
フラッシュ:それをブロンクスでかけたよ。ネルソン、お前が言ってるブロンクスでテクノをかけたやつっていうのは、きっと俺のことだ(笑)。
こういう話をして何時間も笑っていられね。ブルックリンで1枚、マンハッタンで1枚っていう感じで、俺たちがレコード屋を回って集める楽しさを味わっていたことを知って欲しい。ブレイクがあると思って買ったのに無くて「くそっ!」と叫ぶんだ。それで、出来の悪いレコードを良いレコードの間に入れていたよ(笑)。
ネルソン:それ、ドラマに入れるの忘れてたな!
フラッシュ:みんなが俺のレコードをこっそり見て、真似をして買おうとするんだけど、間違ったものを買ってしまうんだよ。そういうことやってDJは楽しんでいたんだ。ほかの奴らより秀でるためにね。
―劇中の「CAN」の「Vitamin C」が印象的でした。
バズ:そう。日本人のリードボーカル(※ダモ鈴木のこと)だよね。ドイツのバンドで、音楽がイケテる(笑)。フラッシュが「CAN」のブレイクを使っていたんだよ。フラッシュは(ブレイクの)変な部分にしか興味がない。彼が興味あるのは「ブン、チッ、チャッチャ、ブン(ビートを口で真似して)」だけ。
フラッシュ:(「Vitamin C」の歌い出しを口ずさんで)「ヘイ、ユー!」、でもほかの部分はくだらないじゃないか(笑)。
バズ:そう、とても過激だ。この作品では、古い音楽も新しい音楽も使っているよ。神がかり的なディスコのスタイルも取り入れている。参加してくれたナイル・ロジャース(※音楽プロデューサー。ドナ・サマーなどの、数々のディスコヒッツを手掛ける。近年では「DAFT PUNK」の「Get Lucky」に参加し、レジェンドとしての風格を見せた)は、ヒップホップにとってのフラッシュのような存在だ。それに、ぼくたちは昔の曲から新しい曲を作ったよ。すでにある曲と他の曲を取り入れて、全く別のものを作る。それがヒップホップというものだからね。
ネルソンがスピーカーから大音量で鳴らされる「クラフトワーク」に衝撃を受けたと話す中で、劇中でも描かれるニューヨークの大停電についても話が及んだ。「あんな音を出せる機材は、その2年前にはなかったんだよ。ブルックリンでそんな大きな音を夜中にかける人はいなかった。つまり、停電の波及効果なんだ。ニューヨーク中の機材があちこちに散らばったんだよ」。
1977年の7月、雷による大々的な停電がニューヨークを襲い、街は一夜にして混沌に陥った。一晩で1,000件を超える放火や盗難が相次ぎ、多大なる経済的損失があった報じられている。しかしながら、それはニューヨークの闇の時代を象徴する事件であると同時に、ヒップホップにとっては必ずしも悪いことではなかったことは、正面切って明言しづらいことではあるが、事実として否定できないところである。劇中においてこの停電のことが描かれ、主人公たちはこの停電のおかげで、ターンテーブルをはじめとする機材を手に入れることになる。当時のことについて、今回のインタビューに応じてくれたもうひとりのキャスト、本作でシャオリン・ファンタスティックを演じたシャメイク・ムーアがフラッシュに尋ねると、なんとも苦笑いを浮かべながらフラッシュは答えた。
シャメイク:ぼくはあの停電(1977年7月13日に起こった)のことを知らなかったんだ。劇中では、停電が起こったとき、みんなターンテーブルとかを持ち出してるけど…あれは本当に起こったこと?
フラッシュ:そうだな…俺は…。
バズ:フラッシュ、まだ時効ではないらしいよ(笑)。
フラッシュ:(笑)停電が起こったとき、俺の隣人が、「フラッシュ、スピーカーたくさん必要だろ?」と言ったんだ。「そうだね。多分ね。僕が持ってるのはゴミだからな」と答えた。そしたら彼らが俺に(スピーカーを)持ってきた。僕は「どこから持ってきたんだ?」と聞いたが、「そんなことはどうでもいい。欲しいか?」「う、うん、欲しい」(笑)と。決して良いこととは言えないけどね、(小声で)まあ助かったんだよ。
<後編へ続く>
協力:Netflix
《シネマカフェ編集部》
特集
この記事の写真
/