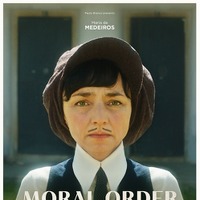海外の映画祭で話題になった作品や、有名監督の新作で、8月末時点で日本の配給が決まっていない作品をピックアップする部門です。従来から継続している部門ですが、今年は海外の映画祭で注目された日本映画も含むことにしました。その日本映画は次回に紹介するとして、今回は8本の欧米作品を紹介します。
『親愛なる同志たちへ』はロシアのアンドレイ・コンチャロフスキー監督の新作です。
1962年、ソ連南部のノボチェルカッスクという町で、ストライキの機運が高まってくる。物資が不足し、人々は不安を抱えて暮らしている。共産党員で役所に勤める女性のリューダは、物資を入手する列に並ばなくて済むような特権を享受しているが、町の不穏な空気の高まりは感じている。リューダの娘はストライキ実行側にシンパシーを寄せており、そんな娘にリューダは警告するが…。
 『親愛なる同志たちへ』
『親愛なる同志たちへ』ソ連時代に実際に起きた最大級のストライキ事件の映画化ですが、この事件自体は隠ぺいされ、ソ連解体後の90年代になるまでその実態が知られることはなかったとのことです。事件の調査を命じられた担当官が、この映画の脚本に参加しており、かなり事実に忠実な作品であると言えそうです。
コンチャロフスキーはそこに母と娘の物語を織り込み、見事な歴史ドラマを完成させています。事態の深刻化と、母の公私に及ぶ不安とがシンクロして肥大化していく様は、熟練の演出によって手に汗を握る展開へとなだれ込んでいきます。共産党の会議の場など、当時のフィルムを流しているのではないかと思わせるくらいに真に迫る美術と撮影が冴え、サスペンスとドラマを盛り上げる演出は、まさに圧巻の一言。
60年代から活動している御年83歳のコンチャロフスキー監督は、現在絶好調であると言えるのではないでしょうか。内容やスタイルを変えながら、精力的に作品を発表しています。大自然を主役に据えた『白夜と配達人』(14)とナチズムを扱った『パラダイス』(16)で連続してヴェネチアの監督賞を受賞したかと思えば、前作『Sin』(19)では、ミケランジェロを主人公にルネサンス期を描く「イタリア映画」を作って驚かせてくれました。間髪置かずに発表された本作もヴェネチアで賞賛され、見事審査員特別賞を受賞しています。これだけ活躍している80代の監督を僕は他に知りません。
ヒロインを演じるユリア・ヴィソツカヤさんが実に見事です、コンチャロフスキー監督とは実生活では夫婦であり、監督の芸術上のパートナーであると言えるでしょう。
第2次大戦を戦ったソ連の兵士に対する敬意、そして労働者の幸福を踏みにじった共産党に対する憎悪など、様々なコンチャロフスキー監督の祖国に対する思いが込められ、それが鮮やかな社会サスペンスドラマへと昇華している結果を見るにつけ、優れた芸術家による創作が達した高みに、感嘆の念を禁じ得ません。
 『デリート・ヒストリー』
『デリート・ヒストリー』『デリート・ヒストリー』はフランスのブノワ・デレピーヌとギュスタヴ・ケルヴェンの共同監督による作品です。今年のベルリン映画祭のコンペティション部門でワールド・プレミア上映されましたが、コメディ作品の受賞は簡単ではないとの一般論を見事はねのけて、銀熊賞に輝いた作品です。本作をとても気に入っていた僕は受賞を知って喝采を叫んだものです。
社会問題を戯画化して笑い飛ばすタイプの作品ですが、単純に商業コーティングされているわけではなく、達者な役者と上手い脚本のおかげで、楽しみながらも考えさせられる高度なコメディドラマに仕上がっています。
郊外に低所得者層が暮らす住宅街というかエリアがあり、まさに社会の周縁で暮らさざるを得ない人々が生きている。それぞれがネット社会に翻弄されており、ネット・ショッピングのやりすぎで、借金で首が回らなくなってしまった男や、ネット予約型個人タクシー(Uberタクシー)のドライバーでネット評価の低さにキレる女性など、現代ならではの問題を抱える人物たち。怒りが頂点に達した時、彼らは無謀な復讐へと向かうのだった…。
現代社会を生きる者であれば、誰もが身に覚えがあるというか、共感できる内容でしょう。ただ、フランス特有な点としては、彼らが「黄色いベスト」と呼ばれるデモに参加していた同志であるという背景が挙げられます。(作業服的な)黄色い反射ベストを着たデモ活動は2018年あたりから毎週末に行われ、現在の政策に幅広く異を唱えるデモへと発展しています。本作の登場人物は、その活動に関わっていた時の高揚感や連帯感と、その後の挫折感のようなものを引きずっており、その意識が現在の行動を縛ってもいます。
というような小理屈をこねるのも楽しいのですが、それはともかくとして、まずはストレートに笑ってもらいたいですね。クレイジーな役をやらせたら当代一のブノワ・ポールヴールドや、『アマンダと僕』で演じた繊細な役とは全く違う面を見せるヴァンサン・ラコストのカメオ出演は最高ですし、とぼけた佇まいがいつも絶品の名優、ドゥニ・ポラリデスが主演を張る作品を見るのは常に至福を伴います。
デリート・ヒストリーというタイトルには、文字通り歴史を消すという意味があるわけですが、現代的には「履歴消去」という意味があるわけで、その二重使いも面白いですね。是非、ご堪能下さい!
 『ラヴ・アフェアズ』
『ラヴ・アフェアズ』もう1本、全く毛色の異なるフランス映画があります。『ラヴ・アフェアズ』、エマニュエル・ムレ監督の新作です。ムレ監督はゼロ年代に頭角を現した恋愛映画の達人で、東京国際映画祭では『チェンジ・オブ・アドレス』(06)をコンペ部門でお招きしています。当時のプログラミング・ディレクターに僕が強く推薦した記憶が蘇ります。あれから14年か!
もちろんムレ監督はその後もコンスタントに作品を作り続けていますが、紹介の機会を逸してきてしまいました。軽快なタッチの作風からスタートしたムレ監督は、その後、歴史ものに取り組んで格調や風雅を身に着け、成長してきた感があります。そして新作『ラヴ・アフェア』は先般フランスで公開され、ムレ監督の最高傑作であるどころか、今年最高のフランス映画かもしれない、と評されています。
小説家志望の青年マキシムには、フランソワという従弟がいて、そのフランソワの妻はダフネ。フランソワを訪ねたマキシムは、彼が帰宅するまでダフネと話し込む。マキシムが現在の恋愛状況について話すと、ダフネはフランソワとの運命的な出会いを語る。やがて、マキシムとダフネにも特別な感情が芽生えたように見えるが…。
延々と続く「恋バナ」を繋げていく内容なのですが(「恋バナ」というよりは「恋愛談義」かな)、そのエピソードがいちいち面白く、そして胸に迫るものがあるのです。映画の中で時制が激しく行き来しても見ていて一切混乱がなく、広大な恋愛タペストリーが敷き詰められていくようです。ついに告白できなかった女性の妹と怪しくなってしまうとか、かなりしょうもない設定もあるのに、妙に格調が感じられるというのは、一体どういうことでしょう。南仏マルセイユ近郊の日差しであるとか、クラシカルなスコアの使用など、映画全体の雰囲気作りに緻密な計算が施されていることが分かります。
マキシムも、そしてダフネも、かなり複雑な事情を抱えており、それが徐々に見えてくる展開にはカタルシスを覚えます。いやあ、これは、上手い。達人、職人の域ですね。恋愛映画を愛する全ての映画ファンにお薦めします。
あ、僕はムレ監督をフランスの今泉力哉と心の中で呼んでいるのですが、いつかふたりに対談をしてもらいたいなあというのが、僕の密かな夢です。
 『ノットゥルノ/夜』
『ノットゥルノ/夜』『ノットゥルノ/夜』はイタリアのジャンフランコ・ロージ監督の新作ドキュメンタリー。今年のヴェネチア映画祭のコンペティション部門に出品された作品です。
言うまでもなく、ロージ監督は『ローマ環状線、めぐりゆく人生たち』(13)でヴェネチア映画祭史上はじめて金獅子賞(1等賞)を受賞し、続く『海は燃えている~イタリア最南端の小さな島~』(16)はベルリン映画祭の金熊賞(1等賞)を受賞するという偉業を成し遂げており、現代のドキュメンタリー作家として孤高の地位を築いている存在であります。
この3年、ロージ監督はイラク、クルディスタン、シリア、レバノンといった国々の国境を訪れ、各地の人々や土地に触れて、映像に記録していったとのテロップが冒頭に流れます。息子たちが拷問死に至った建物を訪れる母親たちが悲嘆に暮れる様を皮切りに、ISISが地域に残した凄惨な傷跡を映画は辿って行きます。破壊された町の様子や、地獄を見てしまった少年少女のあまりに痛ましい心の傷から、事態の深刻さがひしひしと伝わり、見ているこちらの血が凍る思いがします。
しかし、それだけではなく、この映画には至高の美が備わっていて、まさにカメラを構えたそのままのショットが、圧倒的な美と力を伝えてくるのです。それは構図なのか、ショットの持続時間なのか、光の加減なのか、よくわからないのですが、これが映画であるとしか呼びようのない映像の横溢に、言葉を失います。
深い傷を捉える一方で、日々の淡々たる生活にも監督は目を向けて、早朝から鳥撃ちに出かける少年の日々などを通じ、事態は日常を取り戻しつつあるのかもしれないという期待を与えてもくれます。その背後には、国境を静かに守る女性兵士たちからなる部隊の存在があったりもします。
全てが静寂の中で進行し、ゆっくりとしたテンポは我々を落ち着かせてくれる一方で、恐怖の体験を際立たせる効果もあるでしょう。しかし、『ローマ環状線、めぐりゆく人生たち』で都市周縁の人々の暮らしを見つめ、『海は燃えている』では越境移民の現実と一般少年の日常を並置して描いたロッシ監督の関心が、地元の人々から離れることはありません。それが国境のどちら側であるかは、もちろん関係がない。監督が向けるキャメラは、過酷な状況を静かに訴えてくる一方で、人々の明日への希望から目を離すことはないのだと、気づかされます。崇高な1本です。
 『トラブル・ウィズ・ビーイング・ボーン』
『トラブル・ウィズ・ビーイング・ボーン』『トラブル・ウィズ・ビーイング・ボーン』はオーストリアのサンドラ・ヴォルナー監督による作品で、今年のベルリン映画祭に新設された第2コンペ的位置付けの「エンカウンター部門」に出品され、審査員賞を受賞しています。かなりの個性派です。
プールにうつぶせに浮かぶ少女。父親らしき男が引き上げ、再起動する…。少女エリはアンドロイドであり、男は失った娘の代替として、エリにすがっている。それは倒錯した目的にも使用されている。エリは男の扱いを受け入れているが、ある日行方不明になってしまう…。
上の記述だと誤解を招きかねないのですが、欲望の対象としてアンドロイドが使用されるのではなく、アンドロイドはあくまで人間の記憶の受容器として機能します。失った娘の記憶をアンドロイドのエリに託す男の例のように、アンドロイドは有限の存在である人間の記憶を引き受ける装置として存在します。
と言い切れるほど明解な映画ではない、ということを添えておきましょう。全てが、幻想的というか、夢的というか、ざらついてふわふわとして、揺れるような映像の中で描かれていきます。世界観は抽象的で、エンターテイメント・ジャンルとしてのSFとは遠いところに位置します。しかしそこがたまらなく刺激的なのです。
ベルリンの「エンカウンター」部門は、たぶんに実験的で、ミニマルであってもチャレンジングな作品が多く集まる部門でした。ポエティックな残酷性がペシミスティックな未来感を彩る本作は、部門の中でも突出した個性を発揮し、その不思議な美しさは観客を魅了しました。僕も日本で紹介できることに興奮しています。
サンドラ・ヴォルナー監督は本作が長編監督2作目です。すでに自らの美学の映像化に成功しています。そしてアンドロイドのエリを演じるレナ・ワトソンの、表情、メイク、動作など、現代アートの集積のような佇まいから目が離せません。オーストリアからの新たな才能にご注目下さい。
さて、「ワールドフォーカス」部門は今年もラテンビート映画祭と提携をしております。ラテンビートの協賛のもと、以下に紹介する3本のラテン系監督による作品を紹介することが可能になりました。この場を借りて、ラテンビート映画祭に深く感謝します。
 『家庭裁判所 第3H法廷』
『家庭裁判所 第3H法廷』『家庭裁判所 第3H法廷』は、スペインのアントニオ・メンデス・エスパルサ監督の新作です。処女長編の『ヒア・アンド・ゼア』(12)がカンヌ映画祭批評家週間のグランプリを受賞し、続く『ライフ・アンド・ナッシング・モア』(17)はサンセバスチャン映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞しています。東京国際映画祭ではいずれの作品も上映しており、その動向を常にフォローしたい存在であります。
『ライフ・アンド・ナッシング・モア』は、親から事実上ネグレクトされている黒人少年の日々を描く内容でしたが、そのドラマ作りの経験がそのまま本作へと繋がっていると見ることが出来ます。それは、『家庭裁判所 第3H法廷』は、フロリダの裁判所に監督が通い、虐待やネグレクトで親から保護された子どもたちを家庭に戻すかどうかを巡る審議を映像に収めたドキュメンタリーであるからです。実に様々なケースが次から次へと紹介され、いずれもが家庭の悲痛なドラマとなっており、見る者としては厳粛な気持ちにならざるを得ません。
スタイルとしては、完全にフレデリック・ワイズマンの手法であり、『DV1』や『DV2』を直ちに連想する人もいるはずです。僕もそうでした。しかし、それが鑑賞上の妨げになることはありません。むしろ、最良のフォーマットを自家薬籠中の物にしている感があります。
各審議では親に改善の余地があったり、もはや取り返しが付かない状況だったり、各ケースにそれぞれ特有のドラマが含まれています。そういう意味では、究極のヒューマン・ドラマの蓄積であると言っていいかもしれません。
そして、この作品で心に響くのが、法律従事者の真摯な姿勢です。ソーシャルワーカー、弁護士、検事、裁判官、彼らが全て全身全霊をかけて、子どもにとって最善と考えられる措置に向かって邁進します。いずれも個性的な人物たちであり、極めて優秀なプロフェッショナルであることは間違いないですが、それでもその仕事に対する真摯な姿勢には心底感動しますし、敬意の念を抱かずにいられません。
虐待児童を巡る法的解決策の現在を赤裸々に見せてくれると同時に、労働の崇高さをも感じさせてくれる素晴らしいドキュメンタリーです。
 『息子の面影』
『息子の面影』『息子の面影』はメキシコのフェルナンダ・バラデス監督の初長編監督作です。今年の1月のサンダンス映画祭に出品され、高い評価を得ています。
メキシコの辺境地の暮らしを捨て、アメリカを目指して若者が旅発つ。しかし、一切消息が分からず、心配に耐えかねた母親は息子の足跡を辿る。一方で、アメリカから強制送還された別の青年は、やむなく故郷を目指す。母親と青年の歩みは、やがて重なっていく。
バラデス監督は、2010年代に治安が急速に悪化したメキシコの現状を映画に盛り込んでいったといいます。10年代に入り、活動家やジャーナリストが多く殺され、移民や女性への暴力が多く報道されるようになり、監督は危機感を募らせたとコメントしています。
しかし、それが本作に直接的に描かれることはあまりありません。母親は、国境付近で悲惨な事態が起きているらしいと聞き、息子の足跡を辿りますが、その行為は巡礼の旅のようにも映ります。そして故郷を目指す青年の帰還の旅と合わせ、広義にくくれば、ロードムービーの変形であると見ることもできるかもしれません。
しかし、ロードムービーというジャンルに伴うある種の「軽さ」は、あまりにも本作にはそぐわない。本作の主人公たちが辿る道程が負う意味は、あまりにも重いからです。これはもちろん書きませんが、終盤の衝撃度は、今年の映画祭の全作品の中で最大級のものであると予告しておきます。
そして、全編を包む、壮大に美しく荒涼たる大地。路上の死体は息子なのか、その確認を強いられる母親を描く極めてヘヴィーな題材でありながら、大自然はあくまでも悠然と構え、画面には詩情が溢れる。温かみが流れる局面もある。バランス感覚と映画的センスが極めて優れた監督であると舌を巻きます。
そして、決して簡単ではない主題と内容を持つ本作が、サンダンス映画祭では観客賞を受賞しています。これには驚きました。サンダンスの観客、やるなあと思います。東京の観客の反応やいかに! とても楽しみです。
 『老人スパイ』
『老人スパイ』『老人スパイ』はチリのマイテ・アルベルティ監督によるドキュメンタリー作品です。ちょっと緊張を強いる作品の紹介が続いていますが、今作は心の底からホッとできるような、とても温かく優しい作品です。
探偵事務所が、80~90代の職員の募集告知を出す。応募した老人たちは面接を受け、志望動機を語る。愛妻に先立たれ、新たな生きがいを探していたセルジオは見事採用される。そして仕事は、老人ホームの内偵だった! 入居者がひどい扱いを受けているのではないかと疑った身内が、老人ホームの調査を探偵事務所に依頼したのだった。かくしてセルジオはスパイとして老人ホームに「入居」する…!
これだけで面白そうですよねえ。老人ホームにセルジオは正式に入居し、彼の身辺の映画を撮りたいということでカメラクルーは老人ホーム内でカメラを回す許可を得る。しかし、ホーム側も、他の入居者も、セルジオがスパイであることは知らない…、というところがミソ。
前半は、面白いなあ!と素直に設定の特異さに笑いながら楽しんで見ているのだけれど、やがてセルジオが入居者と仲良くなり、彼らの身の上が少しずつ見えてくると、だんだんとこちらにも身につまされる話が多くなり、やがて胸の奥がツーンとしてくるというか、目頭が熱くなるのを止めることが出来なくなります。
日本からはとても遠いチリの話ですが、これほど世界共通の主題はないのではないかというくらい、高齢化社会に生きる我々には切実な作品であると、つくづく思います。意表を突いていて、楽しくて、やがて哀しく、そして染みる…。この作品も、サンセバスチャン映画祭のヨーロッパ作品観客賞を見事に受賞しています(スペイン合作なのでヨーロッパ映画カウントされたのだと思います)。
まさに、老若男女問わずお勧めしたい作品です。
以上、「ワールドフォーカス」欧米作品の8本でした。こちらも1本も逃せないです!
次回も「ワールドフォーカス」作品紹介を続けます。