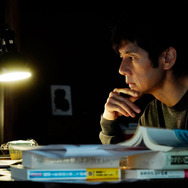多言語演劇「ワーニャおじさん」に込めた思い

舞台演出家である家福は、原作にも出てくるアントン・チェーホフの戯曲「ワーニャおじさん」を多言語演劇として演出するシーンがある。
「人は意味を通じてコミュニケーションをするのが普通です。言葉を使って意味を細分化できるぶん便利ですが、意味の陰に隠れてしまうこともたくさんあるんです。相手の言語が分からないなかでお芝居すると、言葉の意味以外でやり取りをしようとする。それが大事であり、作品の本来の意味にも通じると思ったんです」
「ワーニャおじさん」で登場する言語は、日本語、韓国語、韓国語手話、タガログ語、北京語と多種多様だ。演じる俳優さんたちも、強烈な個性を発揮する。

「みなさん俳優として活動されている方たちを、オーディションで選ばせてもらいました。演技力というよりは、演じる役に合っているかどうかが大前提。あとは、20~30分と短い時間でしたが、人柄の良さと、会話をしたときの理解力が高いなと感じた方にお願いしました。みなさんとても魅力的なお芝居をしてくださいました」
劇中、何度も何度も本読みのシーンが登場する。濱口監督自身も、映画監督として本読みは重視しているのだろうか。
「ここ数年の作品はそうですね。本読みをしていくと、言葉の意味が希薄化していくんです。最初はセリフの意味をダイレクトに受け取り『このセリフを言うのが恥ずかしい』という気持ちが声のなかにも感じられることがあるのですが、本読みを繰り返すことによって、言葉の意味に囚われず、言葉が自動的に出てくるようになる。本番では予期せぬ思いが入ることもあり、言葉の多い映画を撮る上では、有効な方法であるのは確かだと思います。ただ、今後もこういう映画を撮り続けるかは分からないので、やり方は変わるかもしれません」